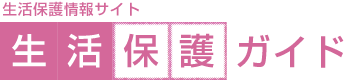生活保護制度の抜本的な見直しを議論している厚生労働省の専門家会議が10月17日に開かれました。
その議論の内容とは・・
年間120億円を超えている生活保護不正受給を減らすために、生活保護申請時や受給時の審査をより厳しくして行こうとする対策の強化に賛成する意見が出た一方、生活保護を本当に必要としている方への支援を閉ざさないよう、不正受給への対策を慎重に行わなければいけないという意見も出ました。また、ひきこもりの方などが働けるよう簡単な作業から始められる「中間的就労」については、貧困ビジネスとして悪用されないよう規制が必要だという意見も。
その背景とは・・
生活保護の受給者は今年6月には211万人超えという過去最多を更新。
今年度の生活保護費の総額は何と、3兆7000億円を超える見通しとされています。
増え続ける生活保護受給者に歯止めをかけなければならないのですが、その中でも生活保護の不正受給は去年3月までの1年間におよそ129億円に上回っていることが大変大きな問題です。
生活保護不正受給への対策については次のとおり検討されています。
【生活保護の不正受給への検討されている対策案】
「自治体の調査権限」の強化
①生活保護申請時の資産や収入の状況に加えて、受給時の就労や生活保護費の支出状況まで調査できる権限を自治体に与える。
②働けるのに働く意思がない方には厳しく対応し、2回生活保護費が打ち切られた後の3回目の申請では、審査を厳しくする。
生活保護の不正受給の増加により、本当に生活に困窮している方が生活保護を受給できなくなるということは避けなければなりません。
厚生労働省の専門会議は今後も生活保護制度の見直しについて議論を重ねたうえで、年内をめどに報告書をまとめることにしているとのことですが、生活保護を必要としている方が本当の意味で救われるためにも、少しでも不正受給を減らす対策を真剣に一刻も早く行っていただき、私たち国民が納めた税金が本当に困った方への支援に回ることを願います。