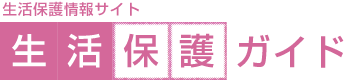全国的に生活保護の不正受給が社会問題となっていますが、その中でも不正受給が目立つ神奈川県では全県初となる、行政と警察が連携した「生活保護不正受給等防止対策連絡会」を今年6月に発足しています。
行政と警察との連携により、神奈川県の生活保護不正受給に対応していく狙いです。生活保護制度の健全化に向け、不正受給の悪質なケースや効果的な対応などについて、行政と警察が情報を共有し、自治体の不正受給等の対策に反映させるとしています。
まず第一段階として相次ぐ生活保護の不正受給を無くすために、行政と警察の連携を強化し、神奈川県内19市中5市(横浜、川崎、大和、横須賀、藤沢)で警察官OBを採用し、さらに複数の市でも検討されています。
生活保護を所管する部署に警察官OBを配置しているのは、横浜、川崎、大和の3市ですが、特に横浜市はことし4月から4人を採用し、横浜市の各区の要請に応じて彼らが出向くといった態勢を取っています。
生活保護窓口での不当な要求の対応のほか、悪質な不正受給が発覚した場合に告発できるか相談するというかたちです。
横須賀、藤沢においては、他部署も含めた窓口での混乱防止対策となっていますが、生活保護の不正受給の相談にも活用するとのことです。藤沢市では、不正受給を告発につなげたケースがあり、「手口は巧妙化しており、警察官OBの知識や経験は役立つ」と話しています。
神奈川県生活援護課によると、2010年度の生活保護の不正受給は1929件であり、前年度から比べると572件も増加しており、金額にすると29.7%増の約10億7500万円にも上っています。
ただ、不正受給の中には働いて得た賃金や年金などの収入を適切に申告しなかったというケースが多く、その割合は生活保護費の総額2433億円の0.44%にとどまるとしています。
神奈川県の生活保護受給者や生活保護支援者からは、「警察による監視強化と受け止められ、生活保護の申請を思いとどまり、孤独死が増えるのでは」と懸念する声も出ています。
生活保護受給者である50代の女性は、「自分も疑われるのでは」という不安を抱き、「生活保護のケースワーカーの調査で十分」と疑問を投げかけているそうです。このほかにも正当に生活保護を受給している方にとっては、警察に頼る姿勢に賛成意見は微妙なところです。
生活保護の不正受給はあってはならないことですが、高収入の人気芸人の親族が受給していたことによって拍車をかけるかたちとなり、生活保護の負の側面だけを目立つ状態にしているとも言えます。神奈川県も含め、全県の生活保護費総額からみても不正受給の割合は極めて低いのが実情であり、わずかな不心得者のために生活保護制度が厳しくなり、本当に苦しい生活をしいられ最後の手段として生活保護を求めている方まで、締め出されてはなりません。
横浜市などのように不正受給を厳しく取り締まることは必要ですが、生活保護制度を見直す動きには、正当に生活保護を受けている方や弱者などへの配慮を十分にした上で、慎重さが要求されます。
生活保護は、「健康で文化的な最低限度の生活」を送る為のセーフティーネットであるので、本当に生活に困窮している方が生活保護から締め出され孤独死につながるような結果になってななりません。
正直に収入などを申告し生活保護を受給している方や、これから生活保護を必要とする方を守れない生活保護制度になっては本末転倒になってしまうので、横浜市などの警察官OBによる不正受給対応は慎重に行うとともに、弱者を守れるような配慮もそれ以上にしていかなければならないでしょう。