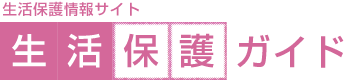本当に必要な生活保護、受けられないネットカフェ難民やホームレス
皆さんは「ネットカフェ難民」という言葉をご存知でしょうか?
ネットカフェ難民とは、アパートの家賃が払えずに追い出されたなどの理由で、ネットカフェに寝泊りをする方たちのことをいいます。
彼らは住所を持たず、1日数千円のアルバイトなどで生計を立てているため、ネットカフェの宿泊費や食事代を差し引くと貯蓄さえできません。
ではネットカフェ難民やホームレスといった、本当に生活に困窮している方々はどうして生活保護を受けられないのでしょうか?
その原因は2つ考えられます。
- 原因①…行政の水際作戦によるもの
- 法律上では、住所がなくても生活保護は受けられます。今お住まいの地域の福祉事務所に行って申請をすることができます。
ですが、厳しい財政難を抱えている行政側は、少しでも生活保護受給者を増やしたくないため、住所がないことを理由に申請を受け付けないことがほとんどです。
若い世代のネットカフェ難民が申請に行っても、まだ働けるからと仕事を探すように指導されるだけで申請すらさせてもらえないケースが非常に多いのが現状です。
- 原因②…情報に接する機会が少ない
- ネットカフェ難民と呼ばれる彼ら自身も、生活保護に対する情報にとぼしく、受けられるということを知らない傾向があります。
生活保護を受けられる条件は整っているのに、情報を得る機会が少ないために申請にまで至らないというケースが多く見受けられます。
ある40代男性は、所定の住所がないために生活保護は受けられないと思いこみ、2か月近くも公園で生活をしていたといいます。
誰もが生活保護や支援制度の情報収集ができる環境を
ネットカフェ難民やホームレスといった方々が、生活保護を受けるためには、正しい情報を得られる環境が必要です。
ネットカフェ難民のように情報を得られる状態が揃っているなら、それをフルに活用して正しい情報を得るのも一つの手だと思います。
また、インターネットなどに接する機会のない方々は、お住まいの地域の福祉事務所や図書館などで情報収集をするという手もあります。
図書館には生活保護に関する本もたくさん置いてあるので、それらを読んで親族に迷惑がかかるのか?いくら貰えるのか?申請に必要な条件は?などを調べてみるのも良いと思います。
そして、公共施設で得た情報とともに、自分が今生活をしている地域の福祉事務所に行って相談をしましょう。
また、自立支援センターを利用することで生活保護を受けずとも、生活を立て直すことができるかもしれません。
- ☆自立支援センター
- 自立支援センターとは、就労意欲があり、働ける状態にある方を対象とした施設です。
原則として入所後3か月以内で就職決定して、自分の貯金でアパート等が借りられるまでの間となっていますが、最大6か月まで延長することができます。
入所中は技能訓練など様々な自立のための支援が受けられるので、それらを活用して就職に役立てましょう。
このように、福祉事務所では様々な支援施設や生活保護の受付を行っています。
まずは、自ら情報を収集することと、就職先を探すことが先決です。
仕事を探していて、自立したいという熱意が伝われば、少なくとも話を全く聞いてもらえずに追い返されることはなくなるはずです。
これからの行政には、ネットカフェ難民やホームレスの方々にもっと多くの情報を得られる環境を整えることが求められているのではないでしょうか。
生活保護について関連記事はこちら
→知っていますか?生活保護の水際作戦
→生活保護自立支援プログラムの成果、18年ぶりに受給率低下
→水際作戦に苦しむ生活保護希望者の声とは?
→本当に健康で文化的?全国一斉生活保護110番に寄せられた声